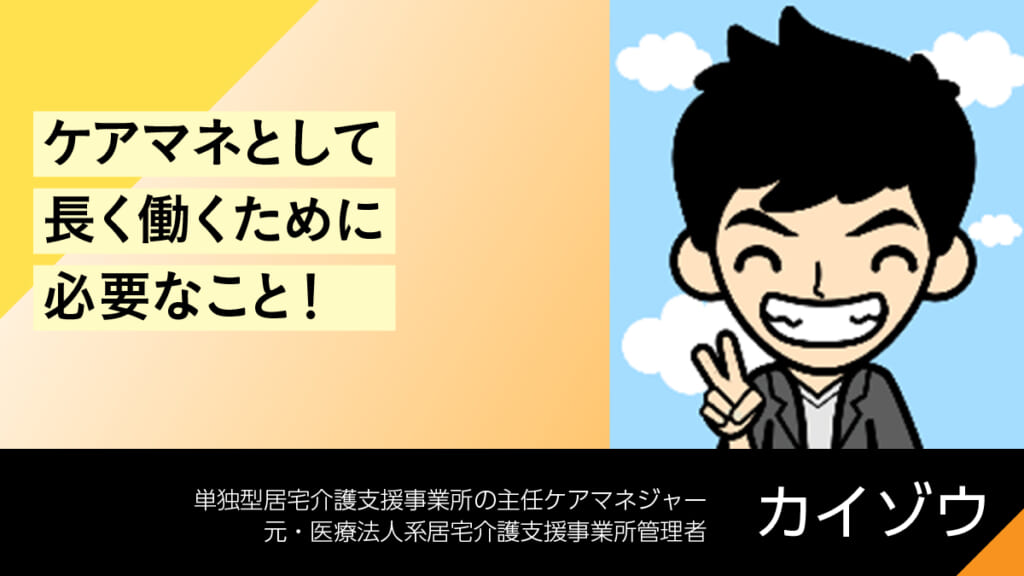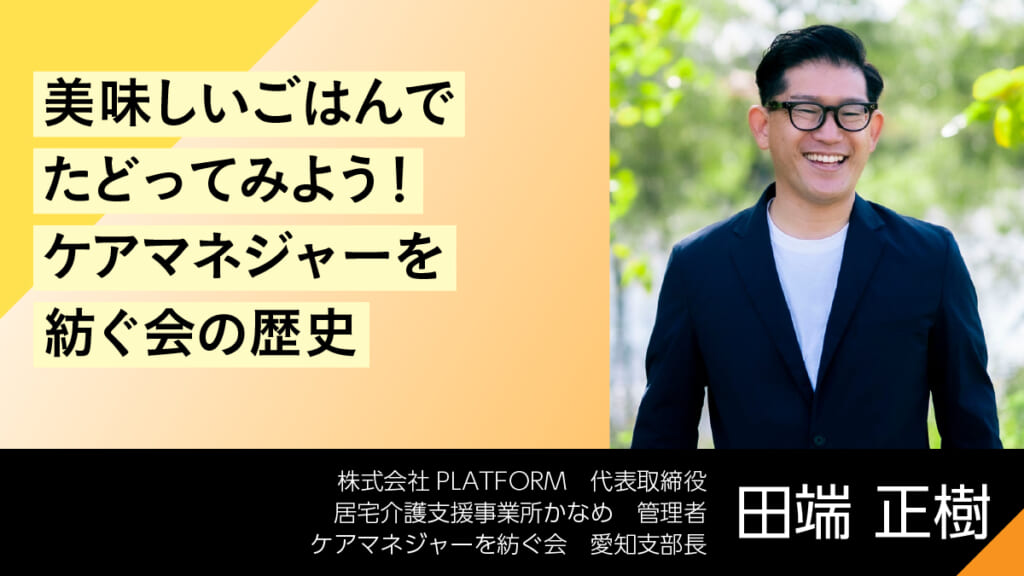介護支援専門員(介護福祉士)
介護事業所コンサルタント
産業ケアマネ
さんかくしおハッカ(高畑俊介)
ケアマネジャーにとっての最高の報酬とはなんだろう。
ケアマネジャーに対する最高の褒め言葉とは何か?
ふいに、そんなことを考えたのです。
ケアマネジャーという仕事は、その性質上、様々な役割を担うことが社会から要求されている職種です。
介護サービスの調整はもちろんのこと、利用者さんやご家族の話をじっくり聞き、その想いを引き出すことも大切な仕事の一つですよね。
さらには、地域の資源を開発したり、埋もれてしまったマンパワーを掘り起こしたりして、高齢者がより良い生活を送れるよう、政策提言を行うこともあります。
このような幅広い役割を担うケアマネジャーにとって、何が最高の「心の報酬」になり得るのでしょうか?
これはもちろん、人によって価値観は異なり、答えは一つではありません。
しかし、私が考える最高の報酬とは、お年寄り本人、家族からいただく「あなたがいてくれてよかった」という言葉に集約されるのではないかと思います。
今回は、この言葉が持つ「本当の意味」を深く掘り下げていくことで、ケアマネジャーの存在意義や仕事の本質について考えてみたいと思います。
「あなたがいてくれてよかった」に込められた意味とは
この「あなたがいてくれてよかった」という言葉には、深い意味が込められています。
それは、単にケアマネジャーとしての職務を果たしたことへの評価ではなく、その人(ケアマネ)自身が存在したことの価値を認められる言葉です。
逆説的ではありますが、ケアマネジャーとして最大限の専門性を発揮した結果、職業としての「ケアマネジャー」という存在が消えてしまうような瞬間が訪れるのです。
つまり、「あなたがいてくれてよかった」と言われるとき、それは「ケアマネジャーの○○さん」ではなく、「○○さん」という個人として評価されている瞬間なのです。
誰でもよかったわけではなく、「あなたでよかった」。この言葉こそ、ケアマネジャーにとって最高の褒め言葉ではないかと思います。
これは、利用者や家族にとって、ケアマネジャーが「専門職」ではなく、信頼できる「人」として認識された瞬間でもあります。
仕事を超えた関係性の中で生まれる言葉だからこそ、より重みを持つのではないでしょうか。

利用者や家族の最期に感じること
この仕事をしていると、多くのお年寄りの最期を見届ける機会があります。人生の最終段階に関わったものとして、通夜や葬儀に参列することも少なくありません。
式が終わるとたいていの場合、親族が弔問客を見送るために出口のところで並んでいますよね。親しい弔問客からは、遺族に慰めや励ましの声がかけられています。
ケアマネジャーである私の存在に気づくと、特別感情を込めてお礼をくださるご家族がいます。
時に、涙を流しながら「○○さんがいてくれてよかった」と言ってくださることもあります。その言葉を聞くと、こちらも本当に救われたような気持ちになるんです。
この瞬間こそ、ケアマネジャーが利用者や家族にとって「欠かせない存在」として心に刻まれた証ではないでしょうか。
介護サービスの枠を超え、人生の大切な場面に立ち会った時、この仕事の本当の価値を再確認する機会となります。
ケアマネジャーは、決してスーパーマンではありません。魔法のようにすべてを解決できるわけでもありません。
それでも、利用者や家族とともに悩み、寄り添い続けることで、いつの間にか支えになっていることがあります。
何もできないかもしれない。
それでも、一緒にいることで、誰かの支えになれるのなら、それだけで十分価値のある仕事なのだと実感します。

どんな仕事にも通じる本質的価値
もちろん、全てのケースでそんな風に思っていただけるわけではありません。
しかしこの考えは、ケアマネジャーに限らず、介護事業者をはじめ、どんな仕事にも当てはまるのかもしれません。
職業の肩書きではなく、個人として評価されること。
その人の存在自体が、誰かにとって価値のあるものになること。
それこそ、どんな仕事においても本質的に目指すべきものではないでしょうか。
人は誰しも、自分の存在が誰かの役に立っていると感じられることで、大きな喜びを得るものです。
特にケアマネジャーの仕事は、人と人とのつながりで成り立っており、信頼関係が何よりも重要です。
だからこそ、「あなたがいてくれてよかった」という言葉の裏にある、信頼の厚さに着目できるのです。
この言葉を励みに、利用者や家族に寄り添い続けることができたら、それだけで十分に価値のある仕事です。
確かに仕事の簡素化や、処遇改善の話は重要です。
ただし、それは仕事が持つ本来の価値を自ら認識しているからこそ、訴えていける議論であるはずです。
私たちがどんなものを大切にし、そしてそれがケアを受ける側にとってどれほど大切なものだったかを伝えていくことで、政治や行政に訴えていかなければいけません。
私たちが年老いて、どんな人々に介護をされたいか。
その考えの先にあるものから、目を背けてはいけません。